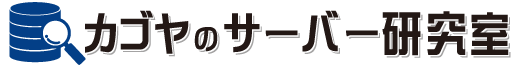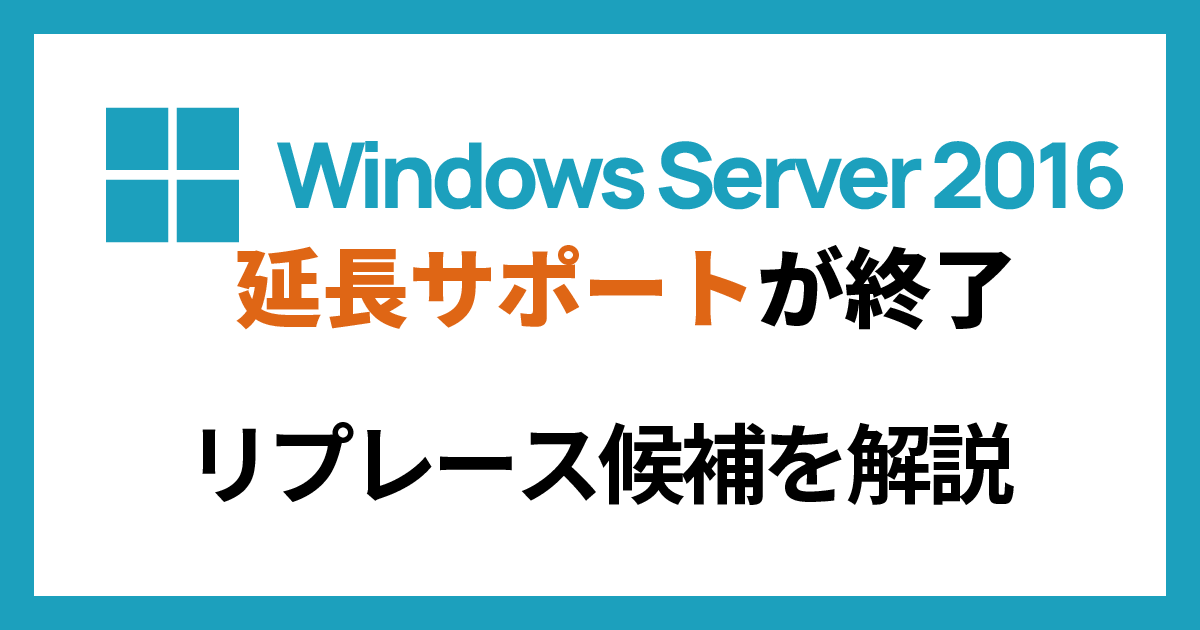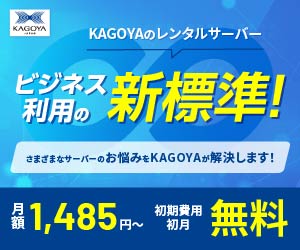システム監視は、企業のITインフラを安定的に運用するための重要な取り組みです。本記事では、システム監視の基本から実践的なポイントまでを詳しく解説します。システム管理者やIT部門の担当者の方々にとって、効果的な監視体制の構築方法や、障害の予防・早期発見のノウハウを学ぶことができます。また、システム監視ツールの選定や導入に関する情報も提供しますので、より効率的なIT運用を目指す企業にとって有益な内容となっています。
目次
システム監視とは
システム監視とは、ITシステムの状態や性能を継続的に観察し、問題や異常を早期に検知することを言います。サーバー、ネットワーク機器、アプリケーションなど、システムを構成する様々な要素の動作状況をリアルタイムで把握します。システムを常時監視することで、安定稼働を維持し、パフォーマンスの最適化を図ることができるのです。
また、潜在的な問題を事前に特定し、迅速な対応を可能にすることで、ダウンタイムの最小化やユーザー体験の向上にも貢献します。システム監視は、現代のITインフラ管理において不可欠な要素となっています。
システム監視の目的・必要性

システム監視の主な目的には、「システム障害発生の予防」と「障害が発生した場合のダウンタイムの最小化」の2つがあります。
常時監視を行うことで、異常の兆候を早期に発見し、問題の発生を予防できます。また、障害発生時に迅速に原因を特定し、適切な対応を取ることで、サービス復旧までの時間を短縮できます。
ここからは、この2つの目的について詳しく見ていきましょう。
システム障害発生の予防
システム監視の重要な目的の一つ目は「システム障害発生の予防」です。これは、システムの異常や問題の兆候を早期に発見し、対処することで、大規模な障害を未然に防ぐことを意味します。例えば、CPUやメモリの使用率が急激に上昇している場合、それはシステムに負荷がかかっている兆候かもしれません。
このような状況を早期に検知し、対策を講じれば、システムに負荷がかかりすぎてダウンすることを未然に防ぐことができます。もし、システム監視を行わない場合、システムがダウンしてから気づくことになり、稼働率や顧客満足度の低下、ひいては経済的損失につながるリスクがあります。
一方、適切にシステム監視を実施していれば、障害発生の前に異常に気づけるので、信頼性の高いサービスを提供し続けることができます。また、データを蓄積することで問題の根本原因を特定しやすくなり、長期的なシステムの改善にもつながります。
障害発生時のダウンタイムの最小化
システム監視のもう1つの目的は、障害発生時のダウンタイムの最小化です。これは、システムに問題が発生した際に、迅速に検知し対応することで、サービスの停止時間を可能な限り短くすることを意味します。
システム監視を行わない場合、障害原因の特定が遅れ、対応開始までに時間がかかってしまい、長時間のサービス停止につながるリスクがあります。これは、ユーザーの不満や信頼低下、さらには経済的損失を招く可能性があります。
一方、適切なシステム監視を実施していれば、原因を早期に特定し、迅速な対応が可能になります。その結果、ダウンタイムを最小限に抑え、サービスの継続性を維持できるのです。これにより、ユーザー満足度の向上や、ビジネスへの悪影響を防ぐことができるでしょう。
システム監視の種類

システム監視は大きく分けて、インフラ監視とサービス監視の2種類に分類されます。インフラ監視は、サーバーやネットワーク機器などのハードウェアやシステムの基盤部分を監視する方法です。一方、サービス監視は、実際にユーザーが利用するアプリケーションやWebサービスの動作状況を監視します。これらの監視を組み合わせることで、システム全体の健全性を把握し、問題の早期発見や迅速な対応が可能となります。それぞれの監視には特定の監視項目があり、システムの特性や重要度に応じて適切な監視方法を選択することが重要です。
| 種類 | 概要 | 主な監視項目 |
|---|---|---|
| インフラ監視 | サーバーやネットワーク機器など、ハードウェアやシステムの基盤部分を監視 | ・Ping監視 ・リソース監視 ・ログ監視 ・SNMP監視 |
| サービス監視 | ユーザーが利用するアプリケーションやWebサービスの動作状況を監視 | ・外形監視 ・プロセス監視 ・URL監視 |
ここからは各監視項目について詳しく説明します。
インフラ監視の監視項目
- Ping監視
- リソース監視
- ログ監視
- SNMP監視
Ping監視
Ping監視は、ネットワーク上のデバイスやサーバーの応答性を確認するための基本的な監視方法です。ICMPプロトコルを使用して、対象機器に小さなデータパケットを送信し、その応答時間を測定します。これにより、ネットワークの接続性や遅延の発生状況を把握できます。
Ping監視は、サーバーやネットワーク機器の稼働状況を迅速に確認できるため、システム障害の早期発見に役立ちます。また、定期的なPing監視を行うことで、ネットワークのパフォーマンスの変化や傾向を分析することも可能です。
シンプルながら効果的な監視方法として、多くのシステム管理者に活用されています。
リソース監視
リソース監視は、システムの健全性を確保するために欠かせない監視項目です。主にCPU使用率、メモリ使用量、ディスク容量、ネットワークトラフィックなどのハードウェアリソースの状態を常時チェックします。
これらのリソースの数値がしきい値を超えると、システムのパフォーマンスが低下したり、最悪の場合はダウンにつながったりする可能性があります。リソース監視を適切に行うことで、問題が大きくなる前に対処でき、システムの安定稼働を維持できるのです。また、長期的なトレンド分析により、将来的なリソース拡張の計画立案にも役立ちます。
ログ監視
ログ監視は、システムやアプリケーションが生成するログファイルを継続的に分析し、異常や問題を検出する重要な監視項目です。サーバーやアプリケーションの動作状況、エラーメッセージ、セキュリティイベントなどの情報をログに記録し、これらを監視することで、システムの健全性や潜在的な問題を把握します。
ログ監視では、特定のキーワードや異常なパターンを検出し、管理者に通知することで、迅速な対応が可能になります。また、長期的なトレンド分析やコンプライアンス要件の遵守にも役立ちます。効果的なログ監視により、システムの安定性向上やセキュリティ強化が実現できます。
SNMP監視
SNMP監視は、ネットワーク上の機器やサーバーの状態を監視する手法です。SNMPプロトコルと呼ばれるネットワーク機器の監視のために作られた通信規格を用いて、対象機器から情報を収集し、異常や性能低下を検知します。ルーター、スイッチ、プリンターなど、多様な機器に対応しており、CPU使用率、メモリ使用量、ネットワークトラフィックなどの重要な指標を監視できます。
また、しきい値を設定することで、問題が発生した際に即座にアラートを発信することが可能です。SNMP監視は、ネットワークインフラの安定性と効率性を維持するために欠かせない監視項目となっています。
サービス監視の監視項目
- 外形監視
- プロセス監視
- URL監視
外形監視
外形監視は、システムやサービスの外部からの可用性や応答性を確認する監視方法です。システムの外側からユーザーがサービスを利用するときと同じようにアクセスして動作の確認をします。
具体的には、Webサイトの表示速度、ログイン機能の動作確認、APIの応答時間などを定期的にチェックします。この監視により、エンドユーザーが実際に体験する可能性のある問題を早期に発見し、対応することができます。外形監視は、内部システムの状態だけでなく、実際のサービス品質を把握するのに役立ちます。
プロセス監視
プロセス監視は、システム上で動作している特定のプロセスの状態を継続的に確認する監視項目です。重要なアプリケーションやサービスが正常に稼働しているかを確認し、異常が検出された場合には即座に対応することができます。
監視対象のプロセスが予期せず停止した場合、自動的に再起動を試みたり、管理者に通知を送ったりすることで、サービスの中断を最小限に抑えることができます。
また、プロセスのリソース使用状況(CPU使用率やメモリ消費量など)も監視することで、パフォーマンス低下や異常な動作を早期に発見することができます。これにより、システムの安定性と可用性を高めることができま
URL監視
URL監視は、ウェブサイトやウェブアプリケーションの可用性と応答性を確認するための監視項目です。外形監視の一種で、特にHTTPでWebアクセスし、可用性を判定するものを言います。
この監視では、特定のURLに定期的にアクセスし、そのページが正常に表示されるかどうかをチェックします。応答時間、ステータスコード、ページの内容などを確認し、異常が検出された場合にはアラートを発信します。
URL監視により、Webサイトにアクセスできない障害をいち早く発見し、ユーザー体験への影響を最小限に抑えることができます。
システム監視を実施する際の注意点

システム監視を実施する際には、いくつかの重要な注意点があります。まず、適切な人員と予算の確保が不可欠です。監視システムの導入や運用には、専門知識を持った人材と十分な資金が必要となります。
また、効果的な監視を行うためには、明確なマニュアルの整備が重要です。監視手順や異常時の対応方法を詳細に文書化することで、チーム全体で一貫した監視が可能になります。これらの要素を適切に準備することで、システム監視の効果を最大限に引き出すことができます。
ここからは各ポイントについて詳しく解説します。
人員や予算が必要
システム監視を効果的に実施するには、適切な人員配置と予算の確保が不可欠です。専門知識を持つ技術者を配置し、24時間365日の監視体制を整える必要があります。
また、監視ツールの導入や保守、アラート対応のための人件費など、継続的な予算確保も重要です。これらのリソースが不足すると、監視の質が低下し、重大な障害を見逃す可能性が高まります。
対策として、監視業務の一部をアウトソーシングしたり、クラウドベースの監視ツールを活用したりすることで、コストを抑えつつ効果的な監視体制を構築することができます。人員と予算の適切な配分は、システムの安定運用と企業の競争力維持に直結する重要な投資と言えるでしょう。
マニュアルの整備が必要
システム監視を効果的に実施するためには、詳細なマニュアルの整備が不可欠です。マニュアルには、監視対象システムの構成、監視項目、アラートの基準値、障害発生時の対応手順などを明確に記載する必要があります。これにより、担当者が交代しても一貫した監視と迅速な対応が可能となります。
また、定期的にマニュアルを見直し、システムの変更や新たな脅威に対応して更新することが重要です。さらに、マニュアルを基にした定期的な訓練を実施することで、緊急時の対応力を高めることができます。適切なマニュアル整備は、システム監視の質を向上させ、障害対応の効率化につながります。
システム監視を行うにはツール導入が不可欠

システム監視を効果的に行うには、専用のツール導入が不可欠です。監視ツールを使用することで、24時間365日の自動監視や、複雑なシステムの一元管理が可能になります。さらに、以下のようなメリットがあります:
- リアルタイムのアラート通知
- 詳細な分析レポートの自動生成
- 見落としやミスの低減
- データの蓄積と分析
代表的なツールとしては、Prometheusがあります。Prometheusは、オープンソースの監視・アラートツールで、多次元データモデルを採用しており、柔軟なクエリ言語を使用してデータを効率的に分析できます。プル型のデータ収集モデルを採用しており、スケーラビリティにも優れています。KAGOYA CLOUD VPSでは、Prometheusのテンプレートを用意しており、簡単に自動構築できます。詳しくは以下のページをご覧ください。
>Prometheusに最適なKAGOYA CLOUD VPS
また、Zabbixも人気の監視ツールです。Zabbixは、エンタープライズ向けの総合的な監視ソリューションで、幅広いプラットフォームをサポートしています。分散監視アーキテクチャを採用しており、大規模なインフラストラクチャの監視にも適しています。Zabbixについては以下の記事をご参照ください。

【初心者向け】Zabbixとは?概要からインストール方法までわかりやすく解説
Zabbixは企業がサーバーやネットワークの監視を行なうときに、必ず名前が上がるソフトウェアです。この記事ではZabbixとは何かや、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。その上でインストール方法も紹介するので、はじめてZabbixについて学ぶ方は是非参考にして下さい。 Zabbixとはオープンソースの統合システム監視ソフトウェア Zabbixとは、サーバーからネットワーク、アプリケーショ…
システム監視ツールの導入はKAGOYAに相談を
システム監視ツールの導入は専門知識が必要な作業ですが、強力なサポート体制を持つKAGOYAなら安心して相談できます。豊富な経験と専門知識を持つスタッフが、お客様のニーズに合わせた最適なソリューションを提案します。
特に、KAGOYA CLOUD VPSでは、Prometheusをテンプレートで自動構築できるため、簡単かつ迅速にシステム監視環境を整えることも可能です。信頼性の高いシステム監視を実現したい方は、ぜひKAGOYAにご相談ください。

Prometheusとは?メリット・デメリットから基本的な使い方までわかりやすく解説
システムを監視するためのツールは、有料・無料のものを含めて数多くの種類があります。 そのなかでも、無料のシステム監視ツールとして人気が高いのがPrometheusです。システム監視を開始する際、Prometheusはまず検討すべき選択肢のひとつと言えます。 この記事では、Prometheusとは何かといった概要からメリット・デメリット、基本的な使い方までわかりやすく解説しました。 この記事を読むこ…